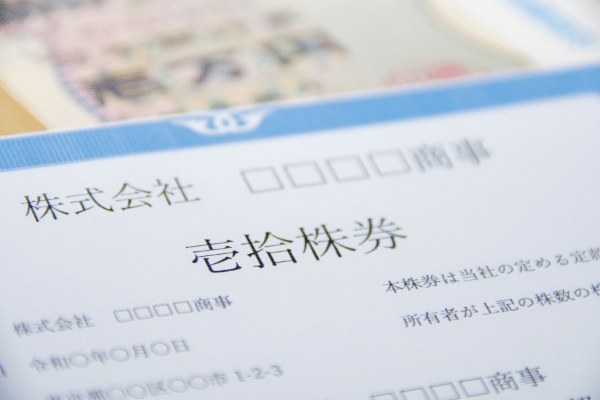
目次
そもそも株とは?
簡単にいえば、株は「企業がお金を集めるために発行する券」です。まずは、株を使ってお金を集める理由から見ていきましょう。
企業が事業資金を調達する際は、銀行からの融資を利用するのが一般的です。融資を受けた場合は、期日までに利息をつけて返済します。
一方で、株によって集めたお金(※出資と呼ばれる)には返済義務がなく、利息を支払う必要もありません。資金調達が将来の負担にならないので、企業にとっては安定経営を実現しやすいというメリットがあります。
イメージを膨らませるために、例を挙げて説明します。
小さな町で定食屋を営むAさんは、確実に人気が出るメニューを考案しました。そのメニューを出せば「店舗を増やせる」と考えましたが、食品を調達したり人を雇ったりするためのお金がありません。
そこでAさんは、お金持ちの友人Bさんにお金を貸してもらおうと考えました。しかし、Bさんから「自分にもメリットがないと貸せない」と言われてしまいました。そこで、Aさんはお金を貸してもらえるように「儲かったら一部の利益を受け取れる券」を作り、その券を持って再度交渉に向かいました。
2回目の交渉は見事に成功し、必要なお金を手に入れたAさんは新メニューの提供を始めました。その後お店は繁盛し、新たに人を雇う余裕もできたため、Aさんは店舗を増やすことができました。
上記の例の「儲かったら一部の利益を受け取れる券」が株にあたります。実際の株式投資では、投資家は自身のお金を出資して株主になり、その代わりに利益の一部が「配当金」という形で株主に支払われます。
株式投資の仕組み
株式投資は、株式会社が発行する株を売買して、売買益や配当金などの利益を狙う投資方法です。この説明だけでは少し難しいので、別の例を挙げて解説します。
定食屋を開いたAさんに出資したBさんは、急に事情が変わってお金が必要になりました。しかし、貸す時に「返さなくてよい」と約束していたため、Aさんに「お金を返してほしい」とは言えません。
困り果てたBさんは、友人のCさんとDさんに相談します。すると、Cさんが「すべての株を10万円で買うよ」と言い、Dさんは「僕なら12万円で買う」と言いました。
5万円で手に入れた株だったので、Bさんは株を売ることにしました。結局BさんはDさんにすべての株を売り、7万円(=12万円-5万円)の利益を手にしました。
このように、出資した企業(※上記の例では定食屋)の業績が拡大すると、その企業の株を購入したいと考える人が増えます。すると、需要と供給の関係から株の価値が高まるため、そのタイミングで株を売ることができれば、最初に購入した人は利益を得られます。
ただし、実際は一般の人が自力で株を買ってくれる人を探すのは難しいでしょう。そこで活用されているのが、投資家が集まる「証券取引所」です。
かつては、証券取引所に多くの人が集まって取引が行われていましたが、現在は証券会社がインターネットなどで取引を管理するようになりました。証券取引所の特徴について見ていきましょう。
| 証券取引所の特徴 | 概要 |
| ①売買できる時間が限られている | 東京証券取引所の取引時間は、平日の9時~11時30分、12時30分~15時。注文自体は取引時間外でも可能だが、売買が成立するのは取引時間のみ。 |
| ②企業の特徴によって市場が分けられている | 大企業や中堅企業、成長企業など、企業の特徴に応じた市場が用意されている。大企業向けのものとしては「東証1部」が有名だが、2022年4月に東京証券取引所が市場を再編するのに伴い、最上位市場は「東証プライム」の呼称に変わる。 |
| ③3つの原則に基づいて売買成立の順番を決める | 取引時間には同時に多くの注文が出るので、「3つの原則」に基づいて優先順位を決めている。 |
【1】価格優先の原則:値段が最も高い(安い)買い注文(売り注文)を優先する
【2】時間優先の原則:発注が早い取引から成立させる
【3】成行(なりゆき)優先の原則:価格を指定していない成行注文(※)を優先する
※価格を指定する注文は「指値(さしね)注文」と呼ばれる
ここまでが株式投資の大まかな仕組みですが、より理解を深めるには後述する魅力や注意点も押さえておく必要があります。
株で利益が出る仕組み
株を買うことによって得られる利益は、大きく以下の3つに分けられます。
- 値上がり益(売買益)
- 配当金
- 株主優待
ここからは3つの利益について、その仕組みや特徴などを見ていきます。
株で利益が出る仕組み1「値上がり益」
値上がり益とは、購入した株を売ることによって得られる利益のことで、専門用語で「キャピタルゲイン」といいます。株を購入した人はその会社のオーナーになり、オーナーには自由なタイミングで株を売る権利があります。
例えば、あなたがある会社の株を1株1,000円で買ったとしましょう。その株が1株1,500円になった時に売却すれば、1株あたり500円(=1,500円-1,000円)の値上がり益となります。
株価が上がったり下がったりする要因はいくつかありますが、特に大きなものとしては「業績」や「将来性」が挙げられます。業績が良い会社、将来性のある会社が現れると、多くの投資家は成長を期待して「株を手に入れたい」と考えます。つまり株の需要が高まることになるので、それに伴って株価は上昇していきます。
一方で事故やトラブルなどによって会社の評判が下がると、株を手放す方が増えて株価が暴落することもあります。世の中に出回っている商品やサービスのように、株も需要と供給のバランスによって価値が変動するのです。
株で利益が出る仕組み2「配当金」
配当金とは、先に例として示した「儲かったら一部の利益を受け取れる券」の「一部の利益」のことです。
配当金の額は各企業が決めており、日本では年に1~2回支払われるケースが多いです。「1株あたり○円」のように計算されるため、持っている株が多いほど配当金を多く受け取れます。
利益が出ているからといって、必ずしも配当金が支払われるわけではありません。配当金の支払いは義務ではないので、中には業績が良くても配当金を出さない企業もあります。
配当金のように継続的に発生する利益は、専門用語で「インカムゲイン」といいます。前述のキャピタルゲインの対になる用語なので、これを機に覚えておきましょう。
株で利益が出る仕組み3「株主優待」
株主優待とは、株を購入してくれた投資家に対して、各企業が贈る特典のことです。具体的には、自社の商品やサービス、割引券、商品券、ポイントサービスなどがあります。
値上がり益や配当金のように現金は受け取れませんが、株主優待の中には日常生活に役立つものが多くあります。現金に換算すると大きな利益になるものあり、テレビや雑誌などでは「株主優待生活」といった特集がよく組まれています。
同じ株を保有していても、株数や保有期間によって特典が変わる株主優待もあります。例えば、大手インテリアメーカーの『ニトリホールディングス』は、株主優待の内容を以下のように設定しています。
・100株以上を1年未満保有している場合:10%の割引券5枚
・100株以上を1年以上保有している場合:10%の割引券10枚
・500株以上を1年以上保有している場合:10%の割引券15枚
保有株数や保有年数によって優待品が変わることもあるので、各企業の株主優待の内容は細かくチェックしておきましょう。
株式投資の魅力
株式投資にはさまざまな魅力がありますが、主なものは以下の3つです。
- 利益を狙える
- 株主優待を受けられる
- 企業を応援できる
それぞれの魅力がどのようなメリットにつながるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
利益を狙える
株式投資の最大の魅力は、やはり利益を狙えることです。中でも大きな利益になりやすいのは、株を売却することで得られる値上がり益です。
例えば、ネット広告大手のサイバーエージェントの株価は、2003年頃まで50円程度でした。当時はあまり注目されていませんでしたが、数々のビジネスを成功させた2022年2月現在の株価は1,500円ほどになっています。
2003年にサイバーエージェントの株を100株(5,000円分)買っておけば、現在は15万円になっている計算です。国内でもこのような大化け株はたくさんあるので、世の中には値上がり益だけで数億円の資産を築いた投資家もいます。
株主優待を受けられる
株主優待は、日々の暮らしの質を高めてくれます。場合によっては値上がり益や配当金よりも大きな利益になるので、優待目当てで株式投資を行っている人もいます。
では、世の中の企業はどのような特典を株主に贈っているのでしょうか。いくつか例を見ながら、株主優待のイメージをさらに膨らませていきましょう。
| 企業名 | 株主優待の内容(一例) |
| オリックス | ・取引先企業の商品を掲載したカタログギフト ・各種サービスの価格を割引 |
| イオン | ・買上金額の3~7%をキャッシュバック ・2,000~1万円のイオンギフトカード |
| 日本たばこ産業 | ・自社グループ商品の贈呈 ・災害復興支援に対する寄付 |
| 全国保証 | ・5,000円分のQUOカード ・5,000円相当の特産品 |
| KDDI | ・3,000~5,000円相当の商品カタログギフト ・提供サービスの割引券 |
(※2022年2月時点)
上記のような株主優待を狙えば、日々の暮らしが充実するでしょう。ただし、優待内容は時期によって異なることもあるので、常に最新の情報をチェックするようにしましょう。
企業を応援できる
あなたが株を購入するために使ったお金は、その企業が成長を目指すための資金になります。企業の経営や成長を支える土台になるので、株式投資を行うとその企業を応援することになるのです。
株式投資において、「この会社を応援したい!」という気持ちは非常に重要です。値上がり益のみを意識していると、株価が予想と逆に動いただけで大きなストレスを感じるでしょう。その企業を応援する気持ちがあれば、多少の値動きは気にならないはずです。
株式投資では「好きな企業の株を買う」というのも立派な方法なので、投資先に迷ったら実践してみてください。
株式投資の注意点
株式投資にはさまざまな魅力がありますが、いくつか注意しておきたいこともあります。具体的には、以下のようなリスクに注意してください。
- 株価の下落リスク
- 倒産リスク
- 希望価格で売却できないリスク
これらのリスクを軽視すると、大切な資金を失いかねません。そのような失敗を防ぐためにも、各リスクの詳細や対策を確認しておきましょう。
株価の下落リスク
株価の下落リスクとは、購入した株の価値が下落することで損失を被るリスクのことです。例えば、ある企業の株価が1,000円から500円に下がると、その企業の株主は1株あたり500円の損失を被ります。
株価の下落リスクは、投資先が少ない方ほど大きくなります。投資資金を1つの株に集中すると、株価が下がった時にカバーするものがありません。株式投資におけるリスクヘッジの基本は、以下のように資金を分散すること(分散投資)です。
・投資する業種を分散する
・投資する地域を分散する(国内と海外など)
・投資するタイミングを分散する(購入する時期を分けるなど)
分散投資は上級者になってからも役立つテクニックなので、初心者のうちから強く意識しておきましょう。
投資企業の倒産リスク
投資していた企業が倒産すると、保有していた株の価値はゼロになります。投資した資金がすべてなくなってしまうため、倒産リスクのある企業への投資は避けなければなりません。
では、実際に倒産した上場企業(※)はどのくらいあるのでしょうか。過去5年間のデータを見てみましょう。
※自社株式を市場に公開している企業のこと。上場企業の株は、一般投資家でも取引できる。
| 時期 | 倒産した上場企業(市場) |
| 2017年 | タカタ株式会社(東証一部) |
| 2018年 | 日本海洋掘削株式会社(東証一部) |
| 2019年 | 株式会社シベール(JASDAQ) |
| 2020年 | 株式会社レナウン(東証一部)株式会社Nuts(JASDAQ) |
| 2021年 | 該当企業なし |
上記の通り、過去5年間で倒産した上場企業は5社で、これは全上場企業の約0.1%にあたります。実際に倒産する企業の株を購入してしまう投資家は存在するので、確率が低いからといって安心せず、取引の前には投資情報をしっかり確認しましょう。
希望価格で売買できないリスク
普段の買い物やオークションと同様に、株の売買も取引相手がいなければ成立しません。「株を買いたい(売りたい)」と考える相手が現れないと、いくら注文を出しても売買できないのです。
特に注意したいのは、保有している株の流動性(※)が以下のような理由で下がってしまった時です。流動性が低い株は、希望する価格では売買できない可能性が高くなります。
※市場に出された売買注文の多さのこと
- 知名度や話題性の低さによって、取引量自体が少ない
- トラブルや事故などの不祥事によって、その株の上場が廃止された
このような流動性のリスクを避けるには、普段から人気があり、頻繁に取引されている株を選ぶことが大切です。
株式投資は数百円でも始められる
「株を購入して企業のオーナーになる」と聞くと、「そんなにお金を持っていないから無理だ」と思うかもしれません。実は株価が高くても、数百円あればその企業のオーナーになることができます。
通常の株式投資では、株の最低取引単位(※「単元」と呼ばれる)が決められています。国内株の場合、1単元は100株に設定されているケースが多く、基本的には100株単位でしか注文できません。例えば『イオン』の株価は約2,600円なので(2022年2月時点)、オーナーになるには26万円(=2,600円×100株)の資金が必要です。
ここまでを読むと「やはり株式投資はハードルが高い」と思うかもしれませんが、証券会社の中には1株や10株から株式取引ができるサービスを提供しているところもあります。このようなサービスは「ミニ株」や「単元未満株」と呼ばれており、それらを提供しているのは以下の証券会社です。
・SBI証券…1株から購入できるサービス「S株」を提供
・マネックス証券…1株から購入できるサービス「ワン株」を提供
・auカブコム証券…1株から購入できる「プチ株」を提供
それでもお金をあまり使いたくない方には、ポイントを使って投資ができる証券会社もあります。例えばポイントサービスが充実している楽天証券では、普段貯めている楽天ポイントで国内株を購入できます。
株式投資を始めるまでの流れ
株式投資に興味を持っても、「手続きが難しそう」「どうやって取引するのかわからない」という方もいるでしょう。申し込みは必要ですが、正しい手順で手続きを進めれば、株式投資を始めることは難しくありません。
【STEP1】取引口座を開設
【STEP2】株を購入
【STEP3】配当金などの受け取り
【STEP4】株を売却
ここからは上記の4つのステップについて、具体的な進め方やポイントなどをわかりやすく解説します。
①取引口座を開設
国内株や外国株は、銀行などの口座では取引できません。株式投資を始めるためには、「証券口座」と呼ばれる専用の口座を開設する必要があります。
証券口座の開設は、証券会社への申し込みによって行います。証券会社ごとにサービスやサポートに違いがあるので、以下の点を比較しながら口座開設先を選びましょう。
・手数料は安いか
・初心者向けのサポートが充実しているか
・取り扱っている商品数は多いか
・お得なポイントサービスやキャンペーンはあるか など
最近では多くの証券会社がWeb申し込みに対応しており、公式サイトから口座開設手続きができます。口座開設先を決めたら、その証券会社のホームページにアクセスし、案内に従って手続きを進めましょう。
②株を購入
証券口座を開設したら必要な資金を入金し、早速気になる株を買ってみましょう。短期売買を繰り返して利益を狙う投資家(※デイトレーダーと呼ばれる)もいますが、投資初心者は長期保有を前提に株を選ぶことをおすすめします。
・需要が長く続く分野かどうか
・売上や利益が伸びているか
・身の回りからヒントを見つける
それぞれのポイントをどのように意識すべきか、以下で詳しく解説します。
- 銘柄選びのポイント1 需要が長く続く分野かどうか
流行している業界は株価が上がりやすく、大きな利益を得られることもあります。しかし、流行は廃れていくものなので、できるだけリスクを抑えたい方は長期的な視点で銘柄を選ぶようにしましょう。
「10~20年後も需要があるか」「技術が進歩しても必要とされるか」といった視点があれば、需要が長く続く銘柄を選びやすくなります。例えば医療や介護、飲食、セキュリティなどは、技術革新によってニーズが変わっても、多くの需要を見込める分野といえます。
- 銘柄選びのポイント2 売上や利益が伸びているか
株式投資における銘柄選びでは、企業の将来性を判断するために業績をチェックする必要があります。業績の中で意識しておきたいデータは、以下の3つです。
| 意識しておきたい業績 | 概要 |
| 売上高 | 企業が商品やサービスの販売によって得た収入の合計金額。 |
| 営業利益 | 本業から得られた利益。売上高から本業にかかった経費を差し引いて計算する。 |
| 経常利益 | 本業以外のものも含めた利益。営業利益から、企業活動の損益を加減して計算する。 |
中でも本業の儲けを表す「営業利益」は、多くの投資家が重視している数字です。本業がうまくいっていない企業は、安定的な成長を期待できないので、銘柄を選ぶ際は必ず営業利益をチェックするようにしましょう。
- 銘柄選びのポイント3 身の回りからヒントを見つける
実は、銘柄選びのヒントは私たちの日常生活の中に転がっています。
例えばテレビや電車の広告、有名人が使っている製品などをチェックすれば、世の中の人が何に興味を持っているのかがわかります。すべての商品・サービスが売れるわけではありませんが、中には「これは爆発的に売れるかもしれない」と感じるものもあるでしょう。
そのような企業を見つけたタイミングで株を買っておくと、将来大きな利益を得られる可能性があります。自分が「このサービスは便利だ」「この商品のこの部分を改善してほしい」と感じたことも銘柄選びのヒントになるので、常にアンテナを張りながら日常生活を送ることをおすすめします。
③配当金などの受け取り
決算が行われるタイミングでその企業の株を保有していると、2~3ヵ月後に配当金を受け取れることがあります。配当金の受取方法は4つあり、それぞれの特徴は以下の通りです。
| 配当金の受取方法 | 概要 |
| ・配当金領収証方式 | 自宅に届く配当金領収証を指定の金融機関に提出することで配当金を受け取る方法。配当金を現金で受け取りたい方におすすめ。 |
| ・株式数比例配分方式 | 使用している証券口座に保有株数に応じた配当金が振り込まれる方式。配当金を使って再投資をしたい方におすすめ。 |
| ・登録配当金受領口座方式 | 証券口座ではなく、指定した金融機関の口座に配当金が振り込まれる方式。すべての配当金を同じ銀行口座で受け取りたい方におすすめ。 |
| ・個別銘柄指定方式 | 銘柄ごとに配当金を振り込む銀行口座を指定する方式。細かく資金管理をしたい方におすすめ。 |
「配当金をどう使うか」によって適した方法が変わるので、配当金の受け取り方は将来のプランも考慮した上で選びましょう。
株を売却する
同じ銘柄を長期間保有する方もいますが、購入した株はいずれ売却することになります。具体的にいつ株を売却すべきなのか、主なタイミングを見てみましょう。
・購入時よりも株価が上昇し、利益が出ている
・想定した範囲を超えて、株価が下落してしまった
・売上高や営業利益など、企業の業績が落ちてきた
・企業の評判が下がるような事故やトラブルが発生した
株価が最も高いタイミングで売り抜くことは難しいため、投資初心者の方は早めに利益を確定させるのが無難です。また、下落した後で上昇する気配がない場合は、ダメージを最小限に抑えるために早めに売却し、他の株に投資することも検討しましょう。
株式投資におすすめの証券会社
国内にはさまざまな証券会社があるため、いざ株式投資を始めようと思っても口座開設先で迷ってしまうかもしれません。そのような方のために、以下では株式投資におすすめの証券会社や、それぞれのおすすめポイントをまとめました。
| 証券会社名 | おすすめのポイント |
| SBI証券 | ・口座開設数1位 ・外国株取扱国数、投信本数1位 ・IPO取扱数1位 |
| 楽天証券 | ・口座開設数2位 ・外国株や投資信託に強い ・ポイントプログラムが充実 |
| マネックス証券 | ・100円からの投資が可能 ・米国株の銘柄数が豊富 ・IPO取扱数2位 |
| 松井証券 | ・少額取引の手数料0円 ・デイトレード専用の信用取引あり ・充実したサポート体制 |
| auカブコム証券 | ・Pontaポイントを使って投資ができる ・デイトレード用の銘柄が充実 ・ミニ株(単元未満株)も取引可能 |
| 岡三オンライン証券 | ・高機能で使いやすい取引ツール ・IPOの当選確率を上げやすい ・投資情報が充実 |
| SBIネオトレード証券(旧ライブスター証券) | ・業界最安水準の手数料 ・投資信託のラインナップが豊富 ・高機能で使いやすい取引ツール |
株式投資はより身近な存在に 積極的にチャレンジしよう
インターネットで取引ができるネット証券が台頭したことで、株式投資は身近な存在になりました。短期的な利益はもちろん、運用方法によっては配当金や株主優待によって生活の充実を図れるので、興味がある方はこれを機に始めてみるとよいでしょう。
ただし、株式投資にはリスクも潜んでいるため、情報収集や分散投資を徹底することが大切です。また、投資情報が充実している証券会社を選んだり、ミニ株(単元未満株)を利用したりすることでも、リスクはある程度抑えられます。
株式投資を始めるにあたって不安を感じた方は、もう一度この記事を読み直し、必要な知識をつけてからチャレンジしてください。

