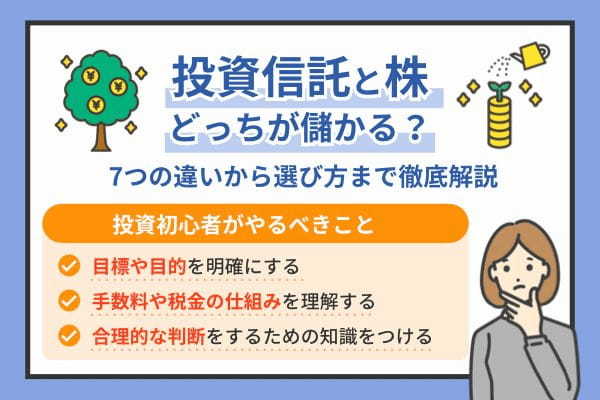
これから投資を始めるにあたって、「株式投資と投資信託はどちらが儲かるのか」と分からない方が多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、株式投資と投資信託のどちらが儲かるのかについて分かりやすく解説します。それぞれの特徴を理解して、ご自身に適した投資先を見極めましょう。
\低コストで投資デビュー/
株式投資とは?
株式投資とは、企業が発行する株式を購入し、保有や売却によって利益を狙う投資手法です。まずはどのようなケースで利益が発生するのか、以下で簡単な例を紹介しておきましょう。
◯株式投資で利益を得る方法
・株価が安いときに購入し、高くなってから売却する(譲渡益)
・購入した株式を保有し続けて、企業から配当金や株主優待を受け取る
基本的に株式投資では上記の方法で利益を得られます。
株式投資で狙える3つの利益
ここでは、株主投資で狙える利益を見ていきましょう。
・譲渡益(キャピタルゲイン)
譲渡益は、株式の売買によって発生する利益です。例えば、1株100円のときに100株を購入し、株価が2倍(1株200円)になってから売却すると、20,000円(100株×2倍)の譲渡益を得られます。
実際の取引では手数料や利益に対して税金が発生するため、譲渡益をそのまま受け取れるわけではありません。
・配当金(インカムゲイン)
配当金とは、企業が稼いだ利益を株主に対して分配するお金のことです。国内では年1~2回ほど分配されるケースが多く、「1株あたり○○円」のように金額が決められています。
配当金の有無は企業によって異なるため、全ての銘柄で受け取れるわけではありません。また、配当金を受け取るには、決算直前にある「権利確定日から翌営業日」まで株式を保有し続ける必要があります。
・株主優待
株主優待とは、企業が株主に対して独自に贈呈する特典のことです。この説明だけではイメージが湧きづらいので、いくつか具体例を紹介しましょう。
◯株主優待の例
・100株以上の保有で、3,000円相当の株主優待券をプレゼント
・300株以上を保有する株主に、カタログギフトをプレゼント
・100株以上を3年間保有する株主に、自社製品をプレゼント
上記のように、株主優待には「保有株数」と「保有期間」に関する条件があります。ただし、いずれも各企業が独自に設定するものなので、保有期間については特にルールがない銘柄も多く存在します。
\Pontaポイントがもらえる!/
投資信託とは?
投資信託は、投資家から集めた資金を1つのファンドにまとめて、投資のプロが代わりに運用する金融商品です。銘柄によって運用方針が異なり、大まかに以下の2タイプに分けられています。
◯投資信託のタイプ
インデックスファンド:平均的なパフォーマンス(指数との連動)を目指す投資信託。
アクティブファンド:指数を上回るパフォーマンスを目指す投資信託。
上記の指数とは、株価や市場の動向を表すものです。代表的な指数には「日経平均株価」や「TOPIX」などがあり、投資信託では運用方針の基準になるベンチマークとして、これらの数が設定されています。
投資信託で狙える利益
投資信託で狙える利益には、「譲渡益」と「分配金」の2つがあります。
・譲渡益(キャピタルゲイン)
譲渡益については、株式投資とほぼ同じ仕組みです。ただし、株式では「株価」が基準となりますが、投資信託の譲渡益は「基準価額」によって決められます。
基準価額は運用成績によって変動し、ほとんどの場合は「1口あたり」や「1万口あたり」の金額が表示されています。
なお、投資信託の購入時・売却時には、実際に反映する基準価額を伏せる「ブラインド方式(※)」が採用されています。
(※)短期的な売買を防ぐなど、公平性を保つために採用されている制度のこと
・分配金(インカムゲイン)
分配金とは、投資信託の運用資金から投資家に分配される資金のことです。「1口あたり○○円」のように金額が決められており、通常は保有口数に応じた分配金を受け取れます。
この分配金は、支払われるタイミングがファンドによって異なります。例えば、「毎月分配型」では、運用成績に関わらず分配金が支払われます。
損失が出ている場合は基準価額から分配金が支払われるため、ファンドの運用資金が減ってしまいます。
\Pontaポイントがもらえる!/
株式投資と投資信託の8つの違い
ここでは、株式投資と投資信託の違いを比較していきましょう。
| 主な違い | 株式投資 | 投資信託 |
|---|---|---|
| 運用主体 | 投資家自身 | 投資のプロ |
| 利益の種類 | 譲渡益、配当金、株主優待 | 譲渡益、分配金 |
| 手数料 | 売買手数料 | 購入手数料、信託報酬、信託財産留保額など |
| 最低投資金額 | 国内株は数万円~数十万円 (※ミニ株の場合は数百円程度) | 1万円程度 (※投信積立では100円から) |
| 銘柄数 | 3,800~4,000銘柄(国内株) | 約6,000銘柄 |
| 取引価格 | リアルタイムの株価を反映 | 1日1回のみ決定 |
| 購入できる場所 | 証券会社 | 証券会社、銀行、投資信託会社 |
| NISAやiDeCo | 一般NISA:○ つみたてNISA:× iDeCo:× | 一般NISA:○ つみたてNISA:○ iDeCo:○ |
| メリット | ・短期的なトレードに適している ・ハイリターンを狙いやすい ・保有コストがかからない | ・プロに運用してもらえる ・少額から始めやすい ・購入できる場所が多い |
| デメリット | ・ハイリスクな銘柄が多い ・自分で運用する必要がある ・一般NISAでしか購入できない | ・保有コストがかかる ・短期的なトレードには向いていない ・ハイリターンを狙いづらい |
| おすすめな人 | ・さまざまな株を短期で取引したい ・短期間で大きな利益を狙いたい ・情報収集や分析が好き | ・コツコツと利益を積み重ねたい ・細かい投資判断が苦手 ・つみたてNISAやiDeCoを利用したい |
上記のた違いについて、1つずつ詳しく解説していきます。
\低コストで投資デビュー/
運用主体:株式投資の場合は投資家自身
株式投資の運用主体は、銘柄を選ぶ投資家自身です。選んだ銘柄の購入はもちろん、売却の判断や権利の行使(議決権など)も自分で行わなければなりません。
一方で、投資信託では「ファンドマネージャー」と呼ばれるプロが、投資家に代わって運用を行います。
株式や債券への投資から、ポートフォリオの構築まで行ってもらえるため、購入・売却の手続きだけで手軽に資産運用を始められます。
利益の種類:譲渡益・配当金・株主優待・分配金
株式投資で得られる利益は、「譲渡益・配当金・株主優待」の3つです。
一方で、投資信託の利益は「譲渡益・分配金」の2つがあり、基本的には長期保有によってリターンを増やしていきます。
一般的には株式投資のほうが大きいリターンを狙いやすく、短期的な売買や成長株への投資によって、資金を2倍以上に増やすような方も見受けられます。
手数料:株式と投信は仕組みが異なる
株式投資と投資信託は、手数料の仕組みが大きく異なります。
| 株式投資の主な手数料 | 投資信託の主な手数料 |
|---|---|
| 売買手数料:株式の取引時に発生する | 購入手数料:商品の購入時に発生する 信託報酬:商品の保有中に毎月発生する 信託財産留保額:解約時や換金時に発生する |
株式投資の売買手数料は、利用する金融機関やプランによって異なります。また、株式投資は運用主体が投資家自身なので、保有中に運用管理費用が発生することはありません。
一方で、投資信託の手数料は商品ごとに決められており、保有中には「信託報酬」と呼ばれるコストがかかります。
銘柄によっては監査報酬や売買委託手数料も発生するので、商品の購入前には手数料の仕組みを調べておきましょう。
\Pontaポイントがもらえる!/
最低投資金額:投信は100円から積み立てられる
株式投資の中でも国内株には、「単元」と呼ばれる最低取引単位が存在します。通常は「1単元=100株」に設定されているため、1株あたり1,000円の銘柄を購入する場合は10万円の資金が必要になります。
一方で、投資信託は1万円程度で購入できる銘柄が多く、さらに大手ネット証券では100円から積み立てられるサービスも提供しています。
そのため、投資信託は手軽に購入しやすい商品として、投資初心者から多くの人気を集めています。
銘柄数:株式は約3,822社・投信は約6,000銘柄
国内株に限定すると、株式投資の対象銘柄は東京証券取引所(以下、「東証」と表記する)に上場している株式が中心です。時期によっても変わりますが、2022年5月現在では3,822社が上場しています。
一方で、大手ネット証券で取り扱われている投資信託は約6,000銘柄です。ただし、つみたてNISAに関しては厳しい基準が設けられているため、対象銘柄は200程度となります。
いずれの銘柄数も金融機関やサービス内容によって変わるため、あくまで目安として参考にしてください。
\低コストで投資デビュー/
取引価格:株式はリアルタイム・投信は1日1回
株式投資の取引価格は、基本的にリアルタイムの株価が反映されます。そのため、短期のトレードを行っている投資家は、チャートの動きを見ながら細かい投資判断を行っています。
一方で、投資信託の取引価格には、リアルタイムの基準価額が反映されません。
取引価格が決められるのは1日1回のみであり、購入・売却をするタイミングでは具体的な金額を把握できない仕組みになっています。
購入できる場所:基本的にネット証券がおすすめ
株式を購入する場合は、取り扱いのある証券会社で口座を開く必要があります。
証券会社であれば、原則として東京証券取引所の上場銘柄を取り扱っていますが、名古屋証券取引所・福岡証券取引所・札幌証券取引所の銘柄や外国株については取扱いがない証券会社も存在するので注意しましょう。
一方で、投資信託は証券会社のほか、銀行や投資信託会社からも購入できます。ただし、銀行などは取扱銘柄が少ない傾向にあるため、基本的にはネット証券からの購入をおすすめします。
NISAやiDeCo:株式は一般NISA・投信は両方購入可能
投資を始めるにあたって、税制優遇制度である「NISA」「iDeCo」の利用を検討する方も多いでしょう。まずは、これらの制度の仕組みを簡単に紹介します。
| 項目 | NISA(ニーサ) | iDeCo(イデコ) |
|---|---|---|
| 概要 | 非課税投資枠における投資による全ての利益が非課税になる | 自分で積み立てた掛金を使って、金融商品を運用する |
| 目的 | 将来のための資産形成 | 老後のための資産形成 |
| 種類 | 一般NISA:年間120万円の投資枠 つみたてNISA:年間40万円の投資枠 ジュニアNISA:未成年を対象にした制度 | 企業が掛金を拠出するタイプは、企業型確定拠出年金(企業型DC)と呼ばれる |
| 節税効果 | 通常の投資ではかかる運用益に対して発生する20.315%の税金が非課税になる | 掛金:全額が所得控除の対象 運用益:全て非課税 給付金:所得控除の対象 |
| 払出し制限 | なし | 原則60歳になるまでは引き出せない |
上記のうち、株式投資で利用できるのは「一般NISA」のみです。投資信託を使えば間接的に投資できますが、他の制度では個別銘柄が対象商品に含まれていません。
一方で、投資信託は上記全ての制度から購入できます。ただし、制度によっては取扱銘柄が限られるので注意しましょう。
\Pontaポイントがもらえる!/
結局、株式投資と投資信託はどっちが儲かる?
株式投資と投資信託のどちらが儲かるのかは、ケースによって大きく異なります。ハイリターンを目指すのであれば、基本的には株式投資が望ましいでしょう。
しかし、投資の世界においてリスクとリターンは比例するため、大きな利益を狙うほど損失が出るリスクも高まります。
一方で、投資信託はローリスク・ローリターン型の銘柄が多いため、安定した資産運用を目指している方に適しています。
ただし、投資信託にもハイリスクな銘柄は存在しており、具体例としては新興国株に投資するもの、資産構成が極端に偏ったものなどが挙げられます。
したがって、投資法や金融商品を選ぶ際には、目標金額や許容できるリスクを踏まえて、運用プランに合ったものを厳選することが大切です。
「どちらが儲かるのか」だけで判断すると、許容リスクを超える恐れがあるので注意しましょう。
\Pontaポイントがもらえる!/
先に証券口座の開設先を探す方法もおすすめ
株式投資と投資信託にはそれぞれ魅力があるため、なかなか1つに絞れない方もいらっしゃるでしょう。そのような方には、先に証券口座の開設先を探す方法がおすすめです。
証券会社によって、サービスやサポートには違いがあります。株や投資信託を取引できる環境も変わってくるので、証券口座の開設で思わぬヒントを得られるかもしれません。
また、早めに証券口座を開設しておくと、以下のメリットが生じる場合もあります。
ポイントプログラムやキャンペーンを比較できる
ポイントプログラムやキャンペーンは、運用成績に大きく影響します。
例えば、株や投資信託を購入する度にポイントが貯まる証券会社では、投資とポイ活の同時進行によってスムーズに資産形成を進められます。
実際に、どのようなポイントプログラムやキャンペーンが存在するのか、以下で紹介しましょう。
| ポイントプログラムの例 | キャンペーンの例 |
|---|---|
| ・取引手数料1%分のポイントが貯まる ・投資信託のクレカ積立でポイント付与 ・投資信託残高に応じたポイントを付与 | ・国内株の入庫で1万円キャッシュバック ・買付手数料を全額キャッシュバック ・投信乗り換えでポイントプレゼント |
ポイントプログラムとキャンペーンにはさまざまなものがあるので、実際の取引をイメージしながら、よりお得な金融機関を選ぶことが大切です。
\低コストで投資デビュー/
手数料やコストを比較できる
証券口座を先に探すと、取引で発生する手数料やコストも細かく比較できます。
特に違いが表れやすいのは、株式投資の売買手数料です。大手のネット証券では、「従量制」や「1日定額制」など複数のコースが用意されており、加入するプランによっても売買手数料は大きく変動します。
以下に、SBI証券の手数料プランを表にまとめました。
| スタンダードプラン (従量制) | アクティブプラン (1日定額制) | ||
|---|---|---|---|
| 約定代金 | 手数料 | 1日の約定代金 | 手数料 |
| 5万円まで | 55円 | 100万円まで | 0円 |
| 10万円まで | 99円 | 200万円まで | 1,238円 |
| 20万円まで | 115円 | 300万円まで | 1,691円 |
各社の料金システムを比較し、できるだけ安く取引できる証券口座を選びましょう。
ポートフォリオを立てやすくなる
ポートフォリオとは「国内株○%」「外国株○%」のように、保有している金融商品の構成比を表したデータのことです。
損失のリスクを抑えた資産運用を続けるためには、1つの銘柄だけに投資するのではなく、複数の銘柄を保有することで適切なポートフォリオを組む必要があります。
このポートフォリオは、各ネット証券が提供しているツールで確認できます。例えば、楽天証券は保有中の金融商品を入力するだけでポートフォリオが円グラフ化される機能を提供しています。
◯ポートフォリオ機能の例
SBI証券:銘柄名や商品分類、数量などを表示したポートフォリオの作成
楽天証券:国内株や投資信託などの資産構成比を円グラフ化
マネックス証券:現在の資産構成比と目標達成率の表示
上記のポートフォリオ機能は、これから購入する予定の商品データを入力することもできます。
実際の取引前に適切な資産構成比になっているのかを確認できるので、ネット証券のポートフォリオ機能は積極的に活用しましょう。
商品を提案してもらえるサポートもある
ネット証券には、投資先になる商品や運用方法を提案してくれるサポートがあります。
◯商品提案型のサポート例
・資産運用に関する相談窓口
・質問形式の銘柄診断
ただし、経験豊富なスタッフやAIによるアドバイスが、必ずしも正しいとは限りません。初心者の判断に比べると高精度かもしれませんが、金融商品の値動きや利回りの予測はプロでも難しいものです。
そのため、上記の商品提案型サポートで提案された投資先や運用方法は、あくまで参考として受け止めることが重要です。
\Pontaポイントがもらえる!/
投資初心者がやるべきこと
ここでは、投資初心者が最初にやるべきことを分かりやすく解説します。株式投資・投資信託のいずれにも共通する内容なので、投資経験が少ない方は確認しきましょう。
目標や目的を明確にする
資産運用の計画は、投資の目的や目標金額を踏まえて組み立てる必要があります。そのため、株式投資や投資信託に興味を持ち始めたら、まずは明確な目標・目的を決めるところから始めましょう。
◯明確にすべき目標や目的
・何のために投資をするのか
・最終目標はいくらなのか
・いつまでに目標金額を達成したいのか
上記の3つが明確になると、必要な投資資金やリターンが分かりやすくなります。
これから何に投資をしたらよいのか考えるヒントにいなるので、目標・目的が決まっていない方はこのプロセスから始めてみてください。
手数料や税金の仕組みを理解する
手数料と税金は、投資を行う上で避けては通れないコストです。いくら利益を出しても、その大部分が手数料と税金で持っていかれるようでは、手元に利益が残りません。
手数料と税金は、それぞれの仕組みを理解するだけではなく、抑えるための対策も考えましょう。
例えば、前述のNISAやiDeCoを利用すると、一定の非課税投資枠内における投資によって発生した利益に対する税金が全て免除されます。
合理的な判断をするための知識をつける
短期間の値動きを見て、購入する銘柄を何となく選んでしまう初心者は少なくありません。
このような投資スタイルは安定性に欠けるため、短期的に儲かることがあっても、長期的に見ると損をする可能性が高くなります。
投資の成功率を上げるには、目標・目的を達成できる運用プランを組み、そのプランに沿った商品を購入する必要があります。
このように合理的な判断ができない場合は、投資や金融商品に関する知識を学ぶところから始めましょう。
時間や労力はかかりますが、必要な知識・スキルを身に付けることが資産を増やす近道になります。
\Pontaポイントがもらえる!/

