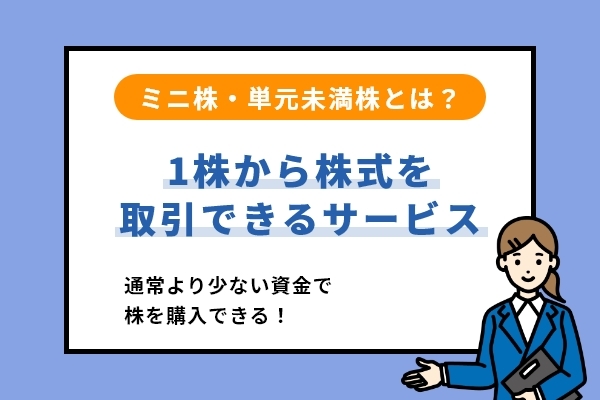投資を始めるにあたって、必要資金は障害になりやすいポイントです。確かに資金が多いほど選択肢は増えますが、実は数百円から始める少額投資にもさまざまなスタイルがあります。
その中でも、本記事では初心者におすすめの少額投資や証券会社をまとめました。少額投資のメリット・デメリットも解説しているので、資産運用に興味がある人はぜひ参考にしてください。
少額投資とは?初心者におすすめの理由
少額投資とは、少ない資金から投資を始める手法です。具体的な金額は人によりますが、利用する証券会社や金融商品によっては、月々数百円から始められる投資もあります。
最近では多くの証券会社が少額投資サービスを展開しており、国内株や米国株、投資信託などを気軽に取引できるようになりました。
なぜ初心者におすすめなのか、3つの理由を紹介します。
おすすめ理由1.数百円から投資を始められる
金融商品にもよりますが、少額投資は数百円から始められる手法です。数百円での投資であれば、資産を大きく失うリスクを避けられます。最大でも同額しか損失が出ないため、仮に投資に失敗しても途中で辞めないで継続しやすくなります。
いきなり資産の大半をつかって投資するのは大きなリスクがあるので、投資初心者は少額から始めることで、資産を失うリスクを抑えつつ、資産形成が行えるようになるでしょう。
おすすめ理由2.分散投資がしやすい
分散投資とは、投資先の資産や時間を分散させることで、損失リスクをコントロールする手法です。
<分散投資のイメージ>
・地域や業種が異なる株式に1株ずつ投資をする
・毎月100円ずつ、同じ間隔で投資信託を積み立てる
・株式や投資信託、債券など、さまざまな金融商品を少しずつ購入する
少額投資では、一つの銘柄や投資1回あたりの必要資金を減らせるため、時期をずらしながら多くの金融商品に分散投資をしやすくなります。
おすすめ理由3.情報収集や分析のきっかけを作れる
実際に金融商品を取引すると、少なからず利益や損失が生じるので、多くの人は情報収集や分析に力を入れるようになります。特に保有銘柄の動向や関連ニュースは、こまめに確認をしたくなるでしょう。そのため、少額投資は本格的な情報収集や分析のきっかけになります。
少額投資を始める方法
少額投資にもさまざまな選択肢があり、数千円~数万円の資金があれば多くの金融商品を取引できます。その中でも、以下では数百円で少額投資を始める3つの方法を紹介します。
単元未満株で株式投資を始める
単元未満株は、通常の株式投資よりも少ない単位で国内株を取引できるサービスです。
通常の株式投資(国内株)では、「1単元=100株」を1単位として取引をする必要があります。例えば、株価が1,000円の銘柄を購入する場合は、少なくとも10万円(1,000円×100株)の資金を用意しなければなりません。
| 銘柄名 | 株価 | 1株の価格 | 1単元の価格 |
|---|---|---|---|
| 日本郵船 | 3,451円 | 3,451円 | 345,100円 |
| トヨタ自動車 | 1,865円 | 1,865円 | 186,500円 |
| 三菱自動車 | 535円 | 535円 | 53,500円 |
上記のように、1株から国内株を取引できるネット証券を選ぶと、必要資金を100分の1に抑えられます。ただし、最低取引単位が10株の証券会社もあるので、サービスの仕組みは事前に確認しておきましょう。
つみたてNISAで投資信託を積み立てる
つみたてNISAは、年間40万円の投資枠から金融商品を購入することで、全てのリターン(譲渡益や分配金)が非課税になる税制優遇制度です。対象商品は投資信託のみですが、幅広い層が利用できるように低リスクのファンドが厳選されています。
ネット証券の中には、100円からつみたてNISAを始められる証券会社がいくつかあります。積立頻度も「毎月・毎週・毎日」などから選べるので、資金が少なくても自分のペースで投資を続けられます。
なお、証券会社によって対象銘柄や積立方法などが異なるので、具体的な運用プランを考えてから口座開設先を選びましょう。
ポイント投資を始める
ポイント投資は、証券会社でためた独自のポイントや、普段から運用しているポイントで金融商品を購入できるサービスです。例として、以下ではSBI証券のポイント投資サービスを見てみましょう。
<SBI証券のポイント投資サービス>
| つかえるポイント | ・Pontaポイント ・Tポイント ・Vポイント ・タカシマヤポイント |
|---|---|
| 対象商品 | 投資信託 |
| ポイント利用単位 | 1ポイント=1円 |
| 利用上限 | なし |
| 利用下限 | 1ポイントから |
| 注文方式 | 金額指定買付 |
| NISAでの利用 | 一般NISA:○ つみたてNISA:× ジュニアNISA:× |
普段からポイ活をしている人は、現金がなくても金融商品を購入できる可能性があります。各社のポイント投資サービスを確認し、つかえるポイントや対象商品を確認してみましょう。
少額投資でおすすめの証券会社
ここからは目的別に、少額投資でおすすめの証券会社をまとめました。どこで始めるか迷っている人は、参考にしながら投資のプランを考えてみましょう。
単元未満株の手数料を抑えたいならSBI証券
手数料を抑えながら単元未満株を取引したい人には、SBI証券がおすすめです。
各社の手数料には取引手数料とスプレッドがあります。取引手数料には購入時と売却時があり、スプレッドでは取引時に値段との差額が上乗せされます。各社の比較は以下の通りです。
| 証券会社名 | 単元未満株の取引コスト |
|---|---|
| SBI証券 (S株) | 購入手数料:0円 売却手数料:約定代金×0.55% 最低売却手数料:55円 |
| auカブコム証券 (プチ株) | 購入手数料:約定代金×0.55% 売却手数料:約定代金×0.55% 最低売買手数料:52円 |
| 大和コネクト証券 (ひな株) | スプレッド:株価の0.5%×株数 売買手数料:なし |
| LINE証券 (いちかぶ) | スプレッド:株価の0.35~1.0%×株数 売買手数料:なし |
| 野村證券 (まめ株) | 購入手数料:約定代金×1.1% 売却手数料:約定代金×1.1% 最低売買手数料:550円 |
SBI証券は売却時の両方で手数料がかかりますが、S株を買い足して100株になった場合は単元株として取引できます。そのるため、1日定額手数料のプランに加入しておくと、1日の約定代金が100万円を超えない限りは手数料がかからないので、売却時のコストを大きく抑えられます。
さまざまな単元未満株を取引したいならSBI証券
単元未満株のラインナップにこだわっている人は、SBI証券から検討してみましょう。SBI証券のS株では、多くの東証上場銘柄が取引対象に含まれています。
<SBI証券の単元未満株>
| サービス名 | S株 |
|---|---|
| 取扱銘柄 | ・東証上場銘柄(プライム、スタンダード、グロース) ・名証上場銘柄(プレミア、メイン、ネクスト) ・福証上場銘柄(新興市場のQ-Boardを含む) ・札証上場銘柄(新興市場のアンビシャスを含む) (※東証以外は売却のみ) |
| 取引口座 | ・特定口座 ・一般口座 ・NISA口座 (※つみたてNISAは対象外) |
SBI証券の公式サイトでは、1株で株主優待を受け取れるS株も紹介しています。さらに、一般NISAやジュニアNISAにも対応しているので、銘柄の選択肢だけではなく投資スタイルの幅も広げられるでしょう。
つみたてNISAを使いたいのならSBI証券
少額からつみたてNISAを始めたい人には、SBI証券がおすすめです。SBI証券の対象銘柄数は業界トップクラスであり、毎月100円からさまざまな銘柄を積み立てられます。
<つみたてNISAの比較表>
| 証券会社名 | 銘柄数 | 積立頻度 | 最低投資金額 |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 188本 | 毎日、毎週、毎月、隔月、複数日 | 100円〜 |
| auカブコム証券 | 183本 | 毎月 | 100円〜 |
| 楽天証券 | 187本 | 毎日、毎月 | 100円〜 |
| マネックス証券 | 163本 | 毎日、毎月 | 100円〜 |
| 松井証券 | 180本 | 毎日、毎月 | 100円〜 |
5つの積立頻度が用意されている点も、SBI証券ならではの魅力でしょう。一般的な毎日・毎月の他にも、隔月や複数日といった積み立て方もできるので、目的や投資資金に合わせて細かく運用プランを調整できます。
また、投資枠を無駄にしない「NISA枠ぎりぎり注文」も用意されているため、SBI証券は年間40万円を使い切りたい人にも向いています。
ポイントのつかいやすさで選ぶならauカブコム証券
地道にためたポイントを有効活用したい人には、auカブコム証券がおすすめです。auカブコム証券では、Pontaポイントをつかって国内株と投資信託を購入できます。
<auカブコム証券のポイント投資>
| つかえるポイント | Pontaポイント |
|---|---|
| 対象商品 | 国内株、投資信託 |
| ポイント利用単位 | 1ポイント=1円 |
| 対象口座 | 一般口座、特定口座、一般NISA口座 |
| サービス利用料 | なし |
ポイントだけでの取引はもちろん、代金の一部にのみポイントをつかえる点も大きな魅力です。つかい道に悩んでいる数ポイントや、日常で余ったポイントを消費できるため、auカブコム証券はPontaポイントを無駄にしたくない人に向いています。
複数のポイントをつかいたいのならSBI証券
ポイ活の幅を広げたい人は、さまざまなポイントに対応しているSBI証券から検討しましょう。ポイント投資の対象商品は少ないものの、SBI証券は独自の方向性でポイントプログラムを充実させています。
<SBI証券のポイントプログラム>
| たまるポイント | ・Pontaポイント ・Tポイント ・dポイント ・JALマイル ・Vポイント ・タカシマヤポイント ・東急ポイント ・アプラスポイント ・Uポイント ・majicaポイント ・QIRAポイント |
|---|---|
| ポイント付与の対象サービス | ・国内株の購入や入庫 ・投資信託の購入や保有 ・SBIラップのおまかせ運用 ・金銀プラチナの購入 ・新規口座開設 ・ユーザーの紹介 ・各種キャンペーン |
| ポイント投資 | ○(投資信託のみ) |
| つかえるポイント | ・Pontaポイント ・Tポイント ・Vポイント ・タカシマヤポイント |
| ポイント利用単位 | 1ポイント=1円 上限:なし 下限:1ポイントから |
| NISAでのポイント投資 | 一般NISA:○ つみたてNISA:× ジュニアNISA:× |
一部はクレカ積立のみ対象ですが、SBI証券ではためるポイントを10種類以上の中から選べます。また、投資につかえるポイントも4種類あるので、普段のポイ活に合わせたプランを立てやすいでしょう。
少額投資のメリット
初心者が少額投資を始めると、どのようなメリットを実感できるのでしょうか。
<少額投資のメリット>
・投資を始めるハードルが低い
・損失のリスクを抑えられる
・投資の経験を積める
・投資を続けやすい
ここからは、上記のメリットを一つずつ解説していきます。
メリット1.投資を始めるハードルが低い
投資を始めるにあたって、必要資金が障害になるケースは少なくありません。例えば、一般NISAの投資枠(年間120万円)を全て使い切ろうとすると、1ヵ月あたり10万円の資金が必要になるため、早々に挫折してしまう人もいるでしょう。
その点、毎月数百円から始められる少額投資なら、缶ジュースやお菓子を買う感覚で気軽に始められます。投資である以上はリスクもありますが、投資資金が少なければ失う金額は大きくありません。
いきなり本格的な投資を始めようとすると、情報収集や分析だけで疲れてしまうこともあるので、まずはハードルが低い少額投資から始めてみましょう。
メリット2.損失のリスクを抑えられる
前述の通り、少額投資は分散投資との相性が良い手法です。
毎月100円ずつのように、購入するタイミングを分散させる形で投資をすると、「少ないときに多く買う」「高いときに少なく買う」を自然と実践できます。この仕組みによって、金融商品の平均購入単価を抑えられます。
投資先の地域や資産を分散させると、一つの金融商品が下落したときのダメージを軽減できます。例えば、国内株が落ち込んでいる一方で、米国株が上昇しているような状況をイメージすると分かりやすいでしょう。
このように、値動きの傾向が異なる金融商品に少額ずつ分散投資をすれば、損失のリスクを大きく抑えやすくなります。
メリット3.投資の経験を積める
貯金が少なくて大きな資金をつかえない人であっても、少額投資なら数百円から投資の経験を積めます。いきなり数百万円単位で投資を始めた場合、1度の失敗で投資を諦めてしまうかもしれません。
少額投資では数百円から行えるので、失敗したとしても継続しやすいといえます。投資の失敗経験を通じて株式の売買のタイミングや分析方法を学ぶことで、投資金額を増やしたときに損失を出す可能性を少しでも減らせるでしょう。
メリット4.投資を続けやすい
少額投資では、一度大負けをしても大金は失いません。特に月々数百円であれば、家計への負担を実感することも少ないので、一喜一憂し過ぎずに投資が長続きします。
投資にはさまざまな法則や規則性があり、中には体感しないと理解できないものもあります。つまり、スキルを伸ばすには続けることが必要になるため、少額投資の続けやすい点は大きなメリットになり得ます。
少額投資のデメリット
初心者には最適な手法のように見える少額投資にも、注意したいデメリットがあります。
<少額投資のデメリット>
・大きなリターンは期待できない
・取引できる商品が限られる
・手数料が割高になりやすい
・短期投資には向いていない
マイナス面にも目を通した上で、自分に合っているかどうかを見極めましょう。
デメリット1.大きなリターンは期待できない
投資の世界において、リスクとリターンは比例するものです。もともと少額投資では、資金を減らすことでリスクを抑えているため、基本的に大きなリターンは期待できません。
例えば、1株=500円のときに国内株を購入し、1株=800円になってから売却するケースを考えてみましょう。この場合、1株しか保有していない人の利益は300円ですが、1万円を投資していた人は6,000円のリターンを得られます。
つまり、少額投資で狙えるリターンには限りがあるので、その点を理解した上で運用プランを立てる必要があります。
デメリット2.取引できる商品が限られる
一般的な規模の投資に比べると、少額投資では取引できる商品が限られます。
分かりやすい例として、米国株の必要資金を紹介しましょう。米国株はもともと1株から取引できる金融商品ですが、ITで有名なアップル社やマイクロソフト社の株価は100ドルを超えています。
少なくとも1万円以上の資金がないと、これらの米国株(現物)は購入できません。他の金融商品についても、数百円と数万円とでは選択肢が変わってくるので、取引できる商品を増やしたい人はある程度の資金を用意しましょう。
デメリット3.手数料が割高になりやすい
基本的に金融商品の手数料は、約定代金によって決まります。投資の規模が大きいほど手数料は増える傾向があるため、「少額投資の手数料は安い」と誤解している人もいるでしょう。
しかし、最低手数料が設けられている金融商品は、いくら約定代金が少なくても一定のコストがかかります。例えば、単元未満株の取引手数料は50~55円程度であることが多く、数百円の取引でもこの金額が徴収されます。
投資資金に対する割合で見ると、少額投資の手数料は割高になりやすいので、金額だけで判断しないように注意しましょう。
デメリット4.短期投資には向いていない
上記の通り、少額投資の手数料は割高になりやすいので、短期売買を繰り返すとコストがかさんでしまいます。取引1回あたりの手数料が50円だったとしても、それを1日に10回繰り返せば500円、1週間では3,500円になる計算です。
また、短期投資では価格の変動幅が限られるため、もともと小さい少額投資のリターンがさらに減ってしまいます。あまりにもリターンが少ないと、手数料だけで赤字になることもあるので、少額投資では長期保有ができる商品・銘柄に目を向けましょう。
少額投資のよくある質問
少額投資は初心者向けといわれますが、実際に始める場合はある程度の知識が必要です。ここからは初心者が押さえたい知識として、少額投資のよくある質問をまとめました。
Q1.まったくの初心者は何から始める?
情報収集や分析が苦手な人には、毎月の積立投資もおすすめです。購入する金額や時期を決めておけば、細かい値動きを毎日のように確認する必要はありません。前述の通り、積立投資には平均購入単価を下げる効果もあるので、最初の投資として検討してみましょう。
Q2.スマホからでも少額投資はできる?
単元未満株やポイント投資をはじめ、近年ではスマホから始められる少額投資も増えています。例えば、SBI証券はスマホ専用の「SBI証券 株アプリ」を提供しており、このアプリでは単元株と単元未満株を同時に取引できます。
また、大和コネクト証券やLINE証券のように、スマホ一つで申し込みから取引まで完結できるネット証券も少なくありません。各社がさまざまなツール・アプリを用意しているので、自分に合ったものを探してみましょう。
Q3.NISA(ニーサ)はどんな制度?
前述でも登場したNISAは、毎年設定される投資枠の範囲内で金融商品を購入することで、全てのリターンが非課税になる税制優遇制度です。一般NISAでは年間120万円、つみたてNISAでは年間40万円の投資枠が設けられます。
また、2024年からは新NISAが始まり、現行制度よりも投資枠や非課税期間が拡充される予定です。
Q4.少額投資で期待できるリターンは?
少額投資で期待できるリターンは、取引をする金融商品や保有期間、投資のスタイルなどによって変わります。参考として、以下では年2.5%の配当金(※)を受け取れると想定して、1,000円を投資したときのリターンを計算してみましょう。
(※)2023年2月時点における、東証プライムの予想平均配当利回りが2.51%。
投資金額×配当利回り=1年間に受け取れる配当金
1,000円×2.5%=25円
なお、実際の株式投資では株価が変動し、取引の際には手数料が差し引かれるため、想定通りのリターンを得られるとは限りません。
Q5.投資はいくらから始めれば良い?
投資を始めるときの資金は、最終的なゴールや目的などを踏まえて、自分自身で決める必要があります。以下では、代表的な金融商品の最低投資金額をまとめたので、参考にしながら計画を立ててみましょう。
<代表的な金融商品の最低投資金額>
国内株(単元未満株):数十円〜
米国株:数十円〜
投資信託:毎月100円〜
他にもさまざまな金融商品があるので、証券会社の公式サイトなどで情報収集をしてみてください。
少額投資を始めて、意識を変えてみよう
少額投資は、初心者が投資を始めるきっかけになる手法です。大きなリターンを狙うことは難しいですが、実際の投資を経験すると意識が変わるため、毎月数百円からでも金融商品を取引してみましょう。
何から始めて良いか分からない人は、本記事で紹介した「おすすめの証券会社」を参考にしながら、自分に合った口座開設先を選んでみてください。